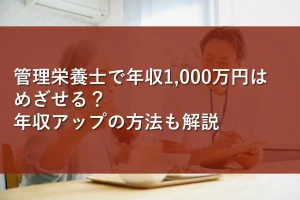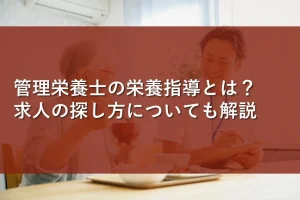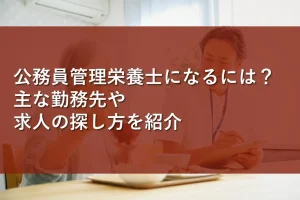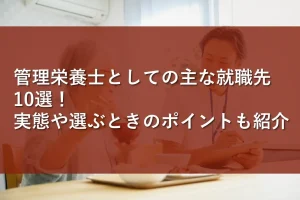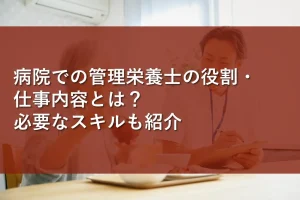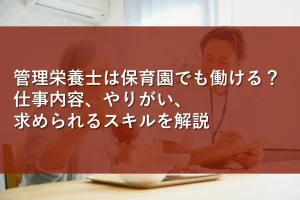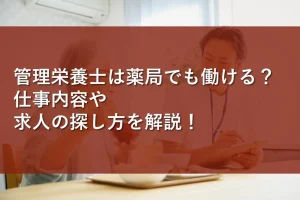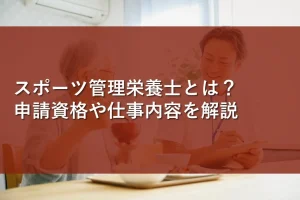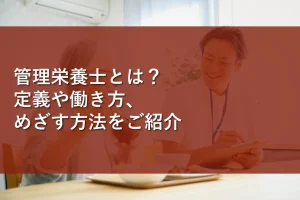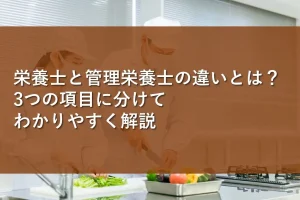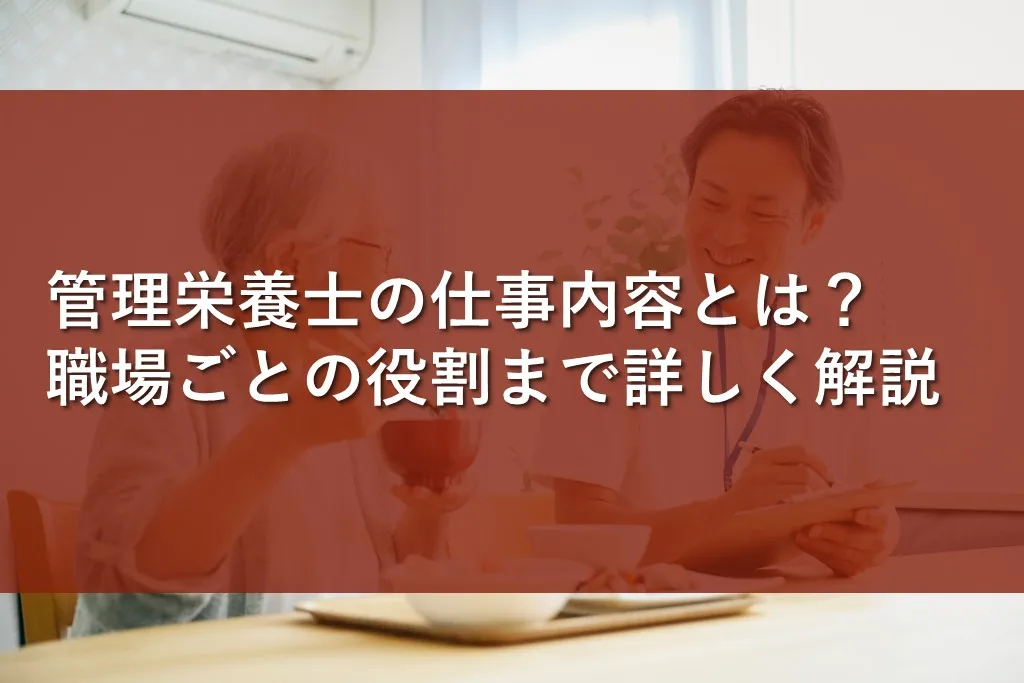
管理栄養士は、食と栄養に関する専門家です。
病院や介護施設、学校、企業など幅広い職場で活躍し、対象者の健康維持・増進のために、適切な栄養管理を行います。
仕事内容は職場によって異なりますが、いずれも高度な専門知識が求められる、やりがいのある仕事です。
目次
管理栄養士の仕事内容
管理栄養士の仕事は幅広く、食育や栄養指導、給食管理など多岐に渡ります。
管理栄養士は、専門的な知識を活かして、対象者に合わせた適切な栄養管理を行うのです。
管理栄養士の仕事内容は、大きく以下の5つに分かれます。
- 食育
- 栄養指導
- 給食管理
- 商品開発
- 相談対応
食育
食育とは、子どもたちが食について正しい知識と習慣を身につけることができるように導くことであり、文部科学省も推進している取り組みです。
食育を行う場所は主に学校や幼稚園・保育所であり、栄養士・管理栄養士の資格とともに栄養教諭普通免許状を保有していると、栄養教諭として指導ができます。
食育の活動は多岐に渡ります。
管理栄養士が携わる最もポピュラーな食育は、栄養教諭による子どもへの食事・栄養バランスなどの授業です。
また、行政の栄養士以外にも、保育園や幼稚園での調理実習や収穫体験など食材に触れる経験から、食事内容について、あるいは箸の持ち方など食事マナーの指導まで、管理栄養士はさまざまな食育に携わります。
管理栄養士は、食事や栄養に関する知識を活かしながら、学校教諭・保育士などと連携して食育活動を企画・提供します。
栄養指導
栄養指導は、対象者の疾患や生活習慣、悩みなどに合わせて食事の相談や食事内容の提案などを行う業務です。
管理栄養士としての知識を活かせる花形的な業務ですが、個人の状態に合わせた提案を行うだけの知識と経験を必要とされる難しい業務でもあります。
栄養指導の流れは以下のとおりです。
- 対象者の栄養状態や食生活を確認・ヒアリング
- 罹患している疾患の特徴や食事との関連の説明
- 食事療法の説明・目標の設定
- 目標をもとにした食生活の実践を記録・評価
- 必要に応じた継続的な栄養指導
栄養指導の対象者は、傷病者から健康な人まで幅広く、入院している人や食生活に不安のある人、食事制限の必要がある人など、さまざまです。
最近では、ダイエット・筋力アップなどを目的としたフィットネスクラブやジムでも、管理栄養士が活躍しています。
給食管理
給食管理とは、保育所や学校、病院、介護施設、社員食堂などの施設での食事を管理することであり、主な仕事内容は以下のとおりです。
- 献立の作成
- 食材の発注
- 調理スタッフの指導
- 食事の調理・提供
- 衛生管理
- 各種帳簿の作成・管理
管理栄養士には施設利用者さんの健康維持を担う役割があります。
そのため、利用者さんに合わせた食事を用意する必要があり、特別な配慮を必要とする方も多いため、給食管理は健康増進に重要な役割を果たしています。
食事を提供する対象によって、献立や調理法を工夫することにも管理栄養士の知識が必要です。
例えば介護現場では、身体の機能が低下している高齢者でも食べやすい調理法や、少量でも栄養が取れる献立を考えることが求められます。
一方、学校現場であれば、成長期の子どもたちに必要な栄養バランスや、地元の食材を使用した食育指導なども考慮して給食を提供します。
商品開発
栄養指導や給食管理以外に、主に食品関連企業や飲食店で商品開発に携わる管理栄養士もいます。
新商品や機能性食品の開発では、栄養の専門知識だけでなく、トレンド把握・競合との差別化などのマーケティングスキルも重要です。
また、レシピ考案だけでなく、その手前の企画・コンセプト立案から携わる場合もあります。
管理栄養士としての専門知識を活かしながら、消費者ニーズをとらえた商品開発を行うことが求められます。
相談対応
管理栄養士の知識を活かし、接客の場や食に関するイベントなどを通して一般の人々の相談にのる場面もあります。
接客の場の例としては、ドラッグストア・調剤薬局や美容クリニックなどが挙げられます。
また、イベントとしては、自治体などの行政機関が開催する、地域住民対象の食や健康に関するイベント・講習会が挙げられるでしょう。
いずれの現場でも、訪れた人の悩みや不安に合わせてアドバイスや指導を行います。
対象が幅広いのが特徴で、子どもから高齢者までの食に関する広い知識が求められます。
悩みに寄り添うための傾聴スキルやコミュニケーション能力も必要不可欠です。
職場ごとに異なる管理栄養士の具体的な役割
管理栄養士の主な仕事内容について説明しましたが、同じ仕事でも職場や提供する対象者によって、求められる役割や必要な知識が異なることがあります。
病院や福祉施設、学校、企業などの職場によって、管理栄養士に求められるスキルや知識は大きく変わってくるのです。
ここでは、以下の職場ごとに、管理栄養士に求められる役割や仕事内容について解説します。
- 医療現場
- 教育現場
- 福祉施設
- ドラッグストア
- ジムやトレーニング施設
- 行政施設
- 企業
医療現場
医療現場で働く管理栄養士の仕事は、主に以下の2つです。
- 患者さんに合わせた給食管理(献立立案・調理・食事提供)
- 患者さんへの栄養指導と管理・NST業務
給食管理では、患者さんの症状・栄養状態・口腔内や嚥下の状態・嗜好などに合わせた食事を提供します。
病状に合わせた適切な食事の提供は、患者さんの疾患の回復を支える重要な役割を果たしています。
食中毒予防のための衛生管理や、時間どおりに適切な食事が提供できるようなシステム作りなども、管理栄養士が行うべき給食管理業務です。
また、病院の管理栄養士は患者さんに対しての栄養指導や、NSTへの参加なども行います。NST(Nutrition Support Team)とは、医師や看護師、薬剤師などとチームを組んで栄養療法に取り組むチームのことです。
NSTで管理栄養士は、栄養上問題のある方をスクリーニングで抽出し、他職種で栄養・食事について検討します。
教育現場
保育園や小中学校などの教育機関では、日々の給食管理業務に加え、子どもたちへの食育活動も大切な仕事です。
成長期の子どもたちがおいしく楽しく栄養を摂取できるよう、季節のイベントなども盛り込みながら給食の献立を作成します。
地域の特産物を使った食事作りや、調理師の負担が少ない調理法の考案、食べ残しを分析して献立を改善していくことも管理栄養士の役割です。
献立の作成や食材の発注以外に、栄養教諭の立場で先生や子どもたちへの食育を行うこともあります。
食事の楽しさや食に関する知識、日本の食文化や行事にまつわる食事などを伝えることも、教育現場で働く管理栄養士の重要な仕事です。
福祉施設
社会福祉施設や介護施設では、施設利用者の栄養管理、献立作成、栄養指導などを行います。
医療機関の業務と同じような仕事ですが、高齢者福祉施設、介護施設の利用者は高齢で食事がとりにくい方が多く、一人ひとりの状況に応じて食事の形状への配慮などが必要です。
例えば、咀嚼力や嚥下機能が低下している方には、刻み食やミキサー食など、食べやすい形状に調整した食事を提供します。
さらに、施設での食事は単なる栄養補給の場ではなく、利用者の楽しみの一つでもあります。
季節の食材を取り入れた献立や行事食を提供し、食事の満足度向上に努めることも管理栄養士の大切な仕事です。
管理栄養士は、施設利用者の日々の健康状態を把握し、無理なく食事を楽しんでもらい、利用者の健康を守る役割を担っています。
ドラッグストア
2016年に健康サポート薬局制度がスタートしたことにより、最近は栄養相談を行うドラッグストアや調剤薬局が増えてきています。
健康サポート薬局とは、通常の調剤薬局の機能に加えて、介護や食事・栄養摂取に関わることを相談できる調剤薬局のことです。
薬局管理栄養士は、来店されたお客さんの栄養相談に応じ、病気予防のためのアドバイス(指導)を行います。
店舗によっては、訪問による栄養指導や食や栄養に関するイベントの企画・開催などの仕事も含まれるでしょう。
管理栄養士としての業務のほか、他の店員と同様に接客やレジ、品出しなどの店舗業務にも対応します。
ジムやトレーニング施設
ジムやフィットネス、トレーニング施設で働く管理栄養士は、ダイエットや体力作り、筋力アップに適した食事内容や、食事の摂取方法などの指導を行います。
トップアスリートから体力作りを目的とした高齢の方々まで、施設や利用者によって対象は異なりますが、どちらも健康な方に向けて栄養面からサポートする仕事です。
トレーニング以外にも、カロリー計算など運動と食事の両面で総合的なサポートを行う施設では、専門的なアドバイスを行える管理栄養士の需要があります。
行政施設
役所や保健所などの行政施設でも、管理栄養士の採用が行われています。
行政で働く管理栄養士は、保健所や市町村の保健センターなどで地域の方に向けた健康施策の実施や評価、健康教室の実施などを行います。
健康教室や食に関するイベントでは、地域の方々から相談を受ける場面もあるでしょう。
不特定多数を対象にした業務が多いことが特徴で、例えば以下のような業務が挙げられます。
- 妊産婦や乳幼児に向けた母子保健事業での栄養相談
- 要介護者や子育て家庭への栄養相談
- 学校や福祉施設などの給食施設への巡回指導
公務員として安定した雇用条件で働けるため、新卒、中途問わず人気が高くなりやすい職種でもあります。
企業
食品会社など、食や健康にまつわる企業でも、管理栄養士の採用があります。
企業の場合、管理栄養士ではなく一般職としての採用が多いものの、食や栄養について高い知識を持つ管理栄養士の需要は高まりつつあります。
特に、食品会社は一般的にも人気があるため、食品会社に就職するために管理栄養士の資格取得をめざす学生も多いです。
企業で働く管理栄養士は、食品の研究開発から商品化、販売後のサポートまで、業務が幅広い点が特徴です。
特に健康機能性食品の開発では、科学的根拠に基づいた機能性の検証や、安全性の確認なども重要な役割となります。
また、品質管理部門や営業部門、広報部門など、社内のさまざまな部署と連携しながら業務を進めることも重要です。
栄養に関する専門知識に加えて、マーケティングの視点やプレゼンテーション能力も求められるでしょう。
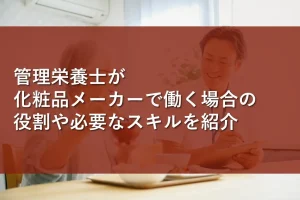
管理栄養士の仕事内容・役割について知っておきたいこと
管理栄養士の仕事内容や役割について、押さえておくべきポイントをいくつか説明します。
管理栄養士にしかできないこと
管理栄養士は、厚生労働大臣の認可による国家資格で、名称独占資格です。
大規模な病院や特定の給食施設では、管理栄養士の配置が義務付けられています。
健康な方から病気の方、高齢で食事がとりづらくなっている方まで、一人ひとりに合わせた栄養指導や管理、給食の管理・提供は、管理栄養士にしかできない仕事です。
そのため、病院や福祉の現場では、管理栄養士にしかできない栄養や食に関する高度な知識が求められます。
管理栄養士と栄養士の仕事内容・役割の違い
管理栄養士と栄養士は混同されやすいですが、別の資格です。
栄養士は都道府県知事の認可による資格で、主に健康な方に対し、栄養指導や給食の提供を行います。
| 管理栄養士 | 栄養士 | |
| 資格の発行元 | 厚生労働大臣 | 都道府県知事 |
| 資格取得の要件 | 管理栄養士国家資格の取得 | 栄養士養成施設を卒業 |
| 対象者 | 健康な人だけでなく傷病者や専門的な栄養指導が必要な人々も含む | 健康な人々が中心 |
詳しくは以下の記事をご覧ください。
管理栄養士としてさまざまな仕事で活躍しよう
管理栄養士は、病院や介護施設、学校、企業など多様な職場で活躍できる職業です。
食や栄養に関する専門知識を活かし、対象者に合わせた適切な栄養管理を行うことで、人々の健康維持・増進に貢献します。
職場によって求められるスキルや知識は異なりますが、どの職場でも「食を通して人々の健康を支える」という管理栄養士の役割は変わりません。
将来管理栄養士をめざす方は、自分の興味や適性に合った職場を見つけ、やりがいを持って働くことができるでしょう。