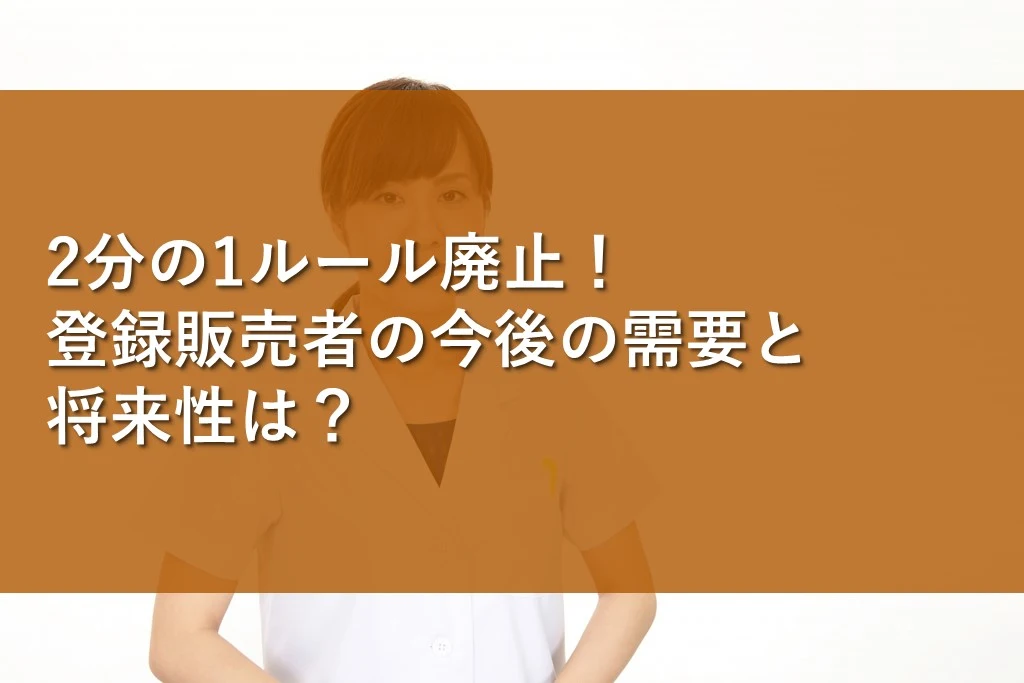
2021年8月1日付でOTC医薬品販売における2分の1ルールが廃止されたことで、登録販売者の今後の動向や需要に注目が集まっています。
厳しい受験資格がないこともあり目指す人が多い登録販売者ですが、2分の1ルールの廃止により今後どのような展開が考えられるのでしょうか。
2分の1ルールがなくなっても、登録販売者の需要が減るわけでは決してありません。
今回は、2分の1ルールが廃止となったあとの登録販売者の現状と将来性、登録販売者が今後活躍できる場所についてくわしく解説します。
目次
OTC医薬品販売の「2分の1ルール」とは?

OTC医薬品販売の2分の1ルールとは、店舗が営業している時間の半分以上の時間、OTC医薬品の販売が可能な薬剤師や登録販売者の常駐を義務とするルールです。
この規定によりドラッグストアでの登録販売者の需要が高まり、そのことが登録販売者を目指す人の数を増やす側面もありました。
2分の1ルールが制定された背景には、消費者が安全に薬を購入できる体制作りがあります。
専門知識のある薬剤師や登録販売者が常駐することで、購入者は安心して市販の医薬品を安心して求められるようになりました。
以上のような理由で導入された2分の1ルールですが、このルールが廃止され、24時間営業の店舗やコンビニで市販の医薬品が販売しやすくなっています。
2分の1ルール廃止で登録販売者はどう変わる?
2分の1ルールの廃止後、気になるのが今後の登録販売者のあり方です。
今までドラッグストアをメインに活躍していた登録販売者ですが、今後はどのように位置づけられていくのでしょうか。
登録販売者の現状と今後の展望を解説します。
登録販売者の現状
2分の1ルールが廃止されたことにより、登録販売者の需要の減少を心配する声があがっています。
まず、登録販売者の現状を見ていきましょう。
登録販売者の受験者数
過去5年間のデータを見ると、登録販売者の資格試験受験者数は年間5万〜6万人です。
| 年度 | 受験者数 | 合格率 |
| 2016年 | 53,369人 | 43.7% |
| 2017年 | 61,126人 | 43.5% |
| 2018年 | 65,500人 | 41.3% |
| 2019年 | 65,288人 | 43.4% |
| 2020年 | 52,959人 | 41.5% |
毎年の受験者数が同水準であることからもわかるように、登録販売者の人気は安定しています。
ドラッグストアに限らず、薬の専門家として登録販売者に医薬品のアドバイスを求める声は数多く、職場で求められて受験する人も見られます。
このような事情も考えれば、今後も登録販売者を目指す人は増えていくことでしょう。
活躍の場
登録販売者は第2類・第3類の医薬品を販売できる資格です。
第2類と第3類で一般市販医薬品の9割を占めているため、多くの店舗で登録販売者が活躍できます。
薬局・ドラッグストアだけでなく、コンビニエンスストア・スーパー・量販店などの小売店、エステサロン・整体院といった体のケアに関わる業種でも需要があります。
近年では、学生のうちに登録販売者の資格をとって就活に役立てる人も増えてきました。
市販薬の専門知識が求められる場所であれば、どこでも働けることが登録販売者の魅力です。
登録販売者の需要

市販医薬品の専門家である登録販売者は、その知識を必要とする現場で求められることもあります。
登録販売者にはどのような需要があるのか、具体的なケースを挙げてご紹介しましょう。
セルフメディケーションの推進
セルフメディケーションには、自分で病気を治すという意味があります。
2017年にセルフメディケーション税制を導入するのにともない、厚生労働省も「軽度の症状の段階で一般市販薬を使用して治す」セルフメディケーションを推進してきました。
市販薬で治せる段階でケアすれば、医師の診断を受ける機会も減るため、医療費も軽減されます。
ただし医薬品には副作用の可能性もあるため、薬の購入には専門家のアドバイスが欠かせません。
的確なアドバイスで薬の説明をしてくれる登録販売者は、セルフメディケーションの推進を助ける役割を担っています。
OTC医薬品の販売
セルフメディケーションとの関係で、登録販売者が担う重要な役割がOTC医薬品の販売です。
第2種・第3種の市販医薬品は手軽に購入できる一方で、効果の説明が受けられないデメリットもあります。
体質は人によって異なるため、同じ種類の医薬品でも同じ効果が得られるとは限りません。
登録販売者は、購入する人の体調やアレルギーなどまで考慮して、その人にあった医薬品を選択するためのアドバイスをします。
医療従事者ではなくても、現在の症状から適切な薬を勧めてくれる登録販売者は、購入者のセルフメディケーションを支える役目を担うでしょう。
地域包括ケアシステムでの窓口業務
地域包括ケアシステムとは、高齢者が自宅で最期まで暮らせるよう、地域ぐるみのバックアップを行う、厚生労働省が推進する体制です。
少子高齢化が進んだ現代では、すべての高齢者の健康を社会保障費だけで支えることが難しくなっています。
これを改善するための取り組みが地域包括ケアシステムで、その窓口業務の役割を期待されているのが登録販売者です。
わざわざ病院に行かなくても、窓口の登録販売者に健康相談するだけで安心できる高齢者もいるでしょう。
セルフメディケーションのアドバイスが求められるケースもあります。
医師や看護師とは違う目線で話せる登録販売者は、地域包括ケアシステムの担い手として高齢者の強い味方となることでしょう。
登録販売者の将来性
2分の1ルールの廃止が多くの登録販売者に不安を与えていますが、今後はどのような展開が期待されるのでしょうか。
今までメイン業務になっていた、店舗勤務以外の業務の将来性を解説します。
資格保有者によるインターネット管理販売
現在、医薬品の説明と販売は店舗における対面での対応のみ、という規制があります。
この現状に対し、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会が規制緩和を要求しており、資格保有者によるインターネットでの管理販売ができるようになるでしょう。
この販売方法なら薬の説明をインターネット上でできるため、登録販売者が店舗に出勤する必要がなくなります。
遠方に住む登録販売者でも、店舗と契約してリモートで勤務できる可能性もあります。
規制緩和には法改正が必要なので、今すぐにではありませんが、将来的な展開としては十分期待できることです。
要指導医薬品の遠隔服薬指導
今後の登録販売者の仕事としては、要指導医薬品の遠隔服薬指導が期待できます。
医療用医薬品の遠隔服薬指導はすでに実現化している ので、要指導医薬品もいずれ規制緩和されるでしょう。
もし要指導医薬品の遠隔服薬指導が開始されれば、登録販売者が活躍できる場も広がるかもしれません。
今後の動向にもよりますが、登録販売者の需要は今後も高まっていくことでしょう。
2分の1ルール廃止により登録販売者がなくなることはない
2分の1ルールの廃止は登録販売者の働き方や需要に大きな影響を与えています。
そのため、不安に感じる有資格者や受験者も多いことと思います。
しかし、より手軽に市販医薬品が手に入るということは、より多くの人が医薬品の説明を求めるということです。
登録販売者の知識を求める現場は、今後も拡大していくものと予想されます。
将来的な可能性も視野に入れて、登録販売者の資格取得を検討してみましょう。






